着物を自分で着られるようになることは、多くの方にとって憧れではないでしょうか。
七五三や成人式、結婚式のお呼ばれなど、人生の節目には着物を着る機会があります。
ですが、「自分で着られるようになりたい」と思っても、何から始めればいいのか戸惑う方も多いのが実情です。
私自身も最初は全くの初心者でした。
せっかくだからと思い切って大学の卒業式に振袖と袴を合わせて自分で着付けをしましたが、襟元が歪み、きれいにできていないのが写真に残ってしまいました。
なんとかしてきれいに着付けができるようになりたいと思い、思い切って着付け教室に通い、基礎から学ぶことにしました。
基礎を習得した後は、より実践的な帯結びや小物の活用方法を学び、お免状も取得し、着物レンタル店で着付けの仕事を少しだけ経験することもできました。
このブログでは、初心者が着物の着付けを学ぶ方法として「教室」と「動画」の活用法を詳しく解説します。
また、必要な道具や料金の相場、資格を取るメリットなども盛り込みました。これから着付けを学びたい方にとって、お役に立てば幸いです。
初心者が着物着付けを学ぶ方法
着付け教室で学ぶメリットとデメリット
着付け教室の一番の魅力は、講師に直接指導を受けられる点です。
特に襟合わせや帯結びは「ちょっとした角度」や「力加減」で仕上がりが大きく変わるため、対面で修正してもらうことは非常に効果的です。
教室によっては少人数制を採用しており、マンツーマンに近い形で丁寧に教えてもらえることもあります。
また、教室では「着物仲間」ができるのも嬉しいポイントです。同じ初心者同士で練習の悩みを共有したり、着物で出かけるイベントに参加できたりと、モチベーションが長続きします。
ただし、通学には費用と時間がかかります。相場は1レッスン3000円前後から、コース全体で数万円かかることも珍しくありません。
仕事や家事で忙しい方にとっては、スケジュールの調整が難しいこともデメリットといえるでしょう。
動画で学ぶメリットとデメリット
現在ではYouTubeやオンライン講座を利用すれば、無料あるいは低コストで着付けを学べます。
動画学習の最大のメリットは、自分のペースで繰り返し学習できることです。
例えば帯結びで手が止まってしまっても、動画を一時停止して何度も見直せます。
一方で、動画はどうしても一方通行の情報提供になります。
そのため「帯の高さがずれている」「襟元が浮いている」など、自分では気づきにくいミスをそのまま続けてしまう可能性もあります。
動画だけで学ぶ場合は、鏡を複数使ったり、スマホで自分を撮影してチェックする工夫が必要です。
教室と動画の併用で効果的に学ぶ方法
おすすめは、教室で基礎を学び、その後は動画で復習する方法です。
教室によっては動画を出しているところもあるので活用しやすいと思います。
また教室専用の動画がない場合でも、同じ内容の動画を参考にして練習するのも一つの方法です。
動画で復習することで、忘れにくくなり習ったことを確実に定着させることができます。
着物着付け初心者が準備すべきもの
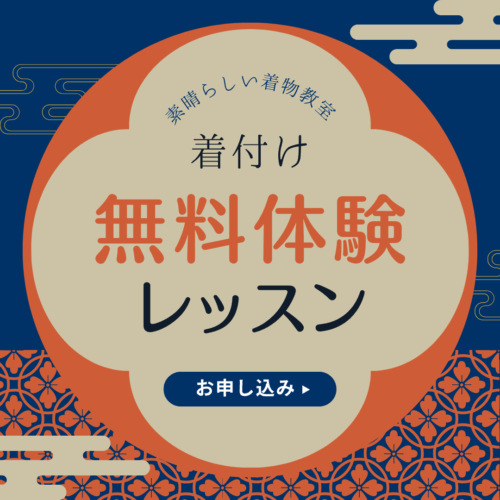
着付けに必要な基本セット
着付けに必要なものは意外と多く、初心者にとっては「何を揃えればいいの?」と迷ってしまいがち。
基本的な小物を以下にまとめました。
- 着物本体 … 小紋や紬など普段着用から始めるのがおすすめ
- 長襦袢 … 着物の下に着るもの。半襟を付けておきましょう
- 帯 … 半幅帯や名古屋帯が初心者向けです
- 帯板…帯の正面をきれいに整える小物です
- 帯枕 … 帯結びの際に帯をきれいな形に整えます
- 帯揚げ…帯の上部に挟んで帯を整えます
- 帯締め…帯結びの仕上げに帯の真ん中で結び、帯の形を整えます
- 腰ひも3本…長襦袢で1本、着物で2本使います
- 伊達締め2本… 着物と長襦袢を固定するために必要です
- コーリンベルト … 襟元の着崩れ防止に使う小物です
- 足袋…白が基本ですが、普段用だと色柄でおしゃれにしてもOK
- 草履 … フォーマル用はかかとが高めで、普段用はかかとが低めのものを使います
これらを一式揃えておくと、初めての着付けにも安心です。
初心者向けのおすすめ着付け小物
初心者は「着付け小物セット」を利用すると便利です。
必要な小物がすべてセットになっており、個別に揃えるよりも経済的で効率的です。
最近ではAmazonや楽天のようなネットショップでも販売しているので、手軽に購入できます。
初心者でも無理なく上達できる学び方
短期間で基礎を習得するための練習の流れ
初心者が無理なく習得するには、段階を踏んで練習することが大切です。
- 下着と補正の準備 … タオルで体型を整えると着崩れ防止に
- 長襦袢の着方 … 襟の抜き加減と襟元の合わせ方がポイント
- 着物の着方 … 腰ひもでしっかり固定し、襟元とおはしよりのバランスを整えます
- 帯結びの練習 … まずは半幅帯から、次に名古屋帯のお太鼓結びへ
- 全体の仕上げ … 鏡で全体のバランスを確認
この流れを1か月ほど繰り返すと、一通り自分で着られるようになります。
七五三や成人式に向けた実践のステップ
- 七五三 … 子ども用の着付けは動きやすさ重視。帯も簡単で華やかな形を選びます。
- 成人式 … 振袖は帯結びのバリエーションが多く、華やかさが重要。教室で集中的に練習するのがおすすめです。
目的に合わせて練習することで、行事当日も落ち着いて着付けができます。
着付けを学んで広がる楽しみ

自分で着物を着る喜びと日常での活用
自分で着物を着られるようになると、着物を着て出かけたくなりますね。
お正月の初詣や京都や奈良のような観光地へのお出かけ、友人との食事会など。
普段の生活に和の彩を添えることができます。
私自身、教室に通ってからは「せっかく練習したから」と着物を着る機会を増やし、日常が少し特別なものに変わりました。
資格取得や仕事に活かせる可能性
着付け教室によっては「師範」や「教授」などのお免状や資格があります。
お免状や資格を取得することで、着付け講師や美容院での着付けスタッフとして仕事をする道も開けます。
実際に私も資格を取得し、結婚式や成人式、卒業式の着付けに入る経験をしました。
自分の技術を活かして誰かの晴れの日をサポートできるのは、大きなやりがいにつながります。
自分で切れるようになるだけでなく、さらにステップアップしたい方には、着付けの仕事を目指すのも一考です。
まとめ
初心者が着物の着付けを学ぶ方法としては、教室と動画の併用がもっとも効果的です。
教室で基礎をしっかり習い、動画で復習を繰り返すことで着実にスキルを身につけられます。
必要な小物を揃えて練習すれば、1か月ほどで一人で着物を着られるようになるでしょう。
さらに資格を取得すれば、趣味を仕事にできる可能性もあります。
日本の伝統文化を大切にしながら、現代の日常にも取り入れていきましょう。
ぜひ着付けを学んで、自分だけの和のライフスタイルを楽しんでみてください。
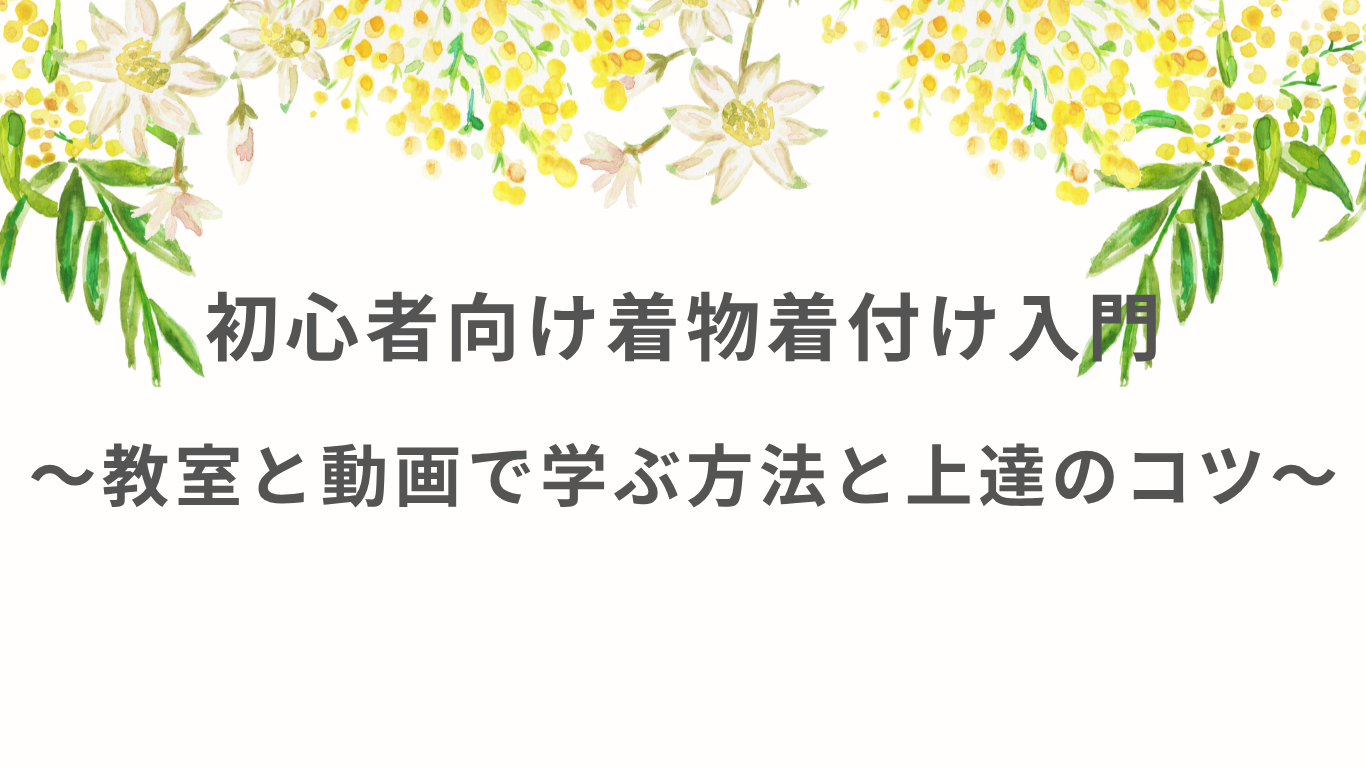
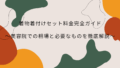
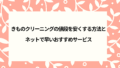
コメント